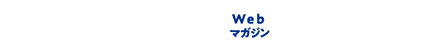そもそも「二次相続」とは?
「二次相続」とは、「2回目の相続」のことです。
例えば夫が死亡し、その財産を妻と子が相続するのが「一次相続」。
その後、妻が亡くなって子が相続するのが「二次相続」です。
「一次」「二次」というのは、法律上の用語ではなく、便宜的に使われている言葉ですが、「二次相続のことまで想定して相続対策を考えること」は非常に大切です。
その理由の一つは、一次相続時の相続財産の分け方により、二次相続時の相続税額が変わり、一次と二次を合わせた相続税額に大きな違いが出ることがあるからです。
簡単な例で見てみましょう。
【例】
夫:遺産(相続財産)2億円
妻:財産(貯金)1億円
夫が亡くなり、2億円の財産を妻と子2人で相続。その後、妻も亡くなる。
【ケース1】
法定の相続分通りに妻が2分の1、子が2分の1(1人あたりでは4分の1)を相続
| 一次相続 | 妻に1億円、子2人に1億円(1人あたり5,000万円) |
|---|---|
| 基礎控除 | 4,800万円(3,000万円+600万円×3人) |
| 妻の相続税額 | 1,580万円(ただし配偶者は16,000万円まで税額軽減により税負担なし※) |
| 子2人の相続税額 | 1,120万円(1人あたり560万円) |
| 納税額 | 1,120万円(税額はすべて速算表による概算) |
| 二次相続 | 子2人に、妻から2億円(夫の遺産1億円+貯金1億円) |
|---|---|
| 基礎控除 | 4,200万円(3,000万円+600万円×2人) |
| 子2人の相続税額 | 3,340万円(1人あたり1,670万円) |
| 納税額 | 3,340万円 |
一次+二次相続の合計の相続税額:4,460万円
※配偶者の税額軽減-配偶者が受け取る財産のうち法定相続分または1億6,000万円までは相続税を払う必要がない。
【ケース2】
妻が遺産の30%、子が70%(1人あたりでは35%)を相続
| 一次相続 | 妻が6,000万円、子供2人が14,000万円(1人あたり7,000万円を相続) |
|---|---|
| 基礎控除 | 4,800万円(3,000万円+600万円×3人) |
| 妻の相続税額 | 712万円(ただし配偶者は16,000万円まで税額軽減により税負担なし※) |
| 子2人の相続税額 | 1,792万円(1人あたり896万円) |
| 納税額 | 1,792万円 |
| 二次相続 | 子2人に、妻から1億6,000万円(夫の遺産6,000万円+貯金1億円) |
|---|---|
| 基礎控除 | 4,200万円(3,000万円+600万円×2人) |
| 子2人の相続税額 | 2,140万円(1人あたり1,070万円) |
| 納税額 | 2,140万円 |
一次+二次相続の合計の相続税額:3,932万円
一次二次合計で同額を受け取っても相続税額は異なる
上記のように、法定相続分で相続した【ケース1】のときより、子供が多く一次相続するように遺産分けをした【ケース2】の時の方が、一次、二次合わせた納税額が500万円以上少なくなります。
どちらのケースでも、子供が父親と母親から受け取る遺産額の合計は1人あたり1億5,000万円で変わりません。しかし、相続税額は大きく異なってくるのです。
このケースでは、母親が1億円の貯金を持っていました。
そのため、一次相続時に法定相続分として2分の1を受け取ってしまうと、二次相続で子供に残す金額が大きくなり相続税額が大きくなってしまうのです。
母親が一次相続でアパートなどの収益物件を相続した場合も、そこから現金収入が積み上げられ、母親の資産を大きくすることが考えられます。
その場合も、二次相続で子供が受け取る遺産額を大きくして、相続税負担を増やすことになります。これも一次相続の際に気を付けるポイントでしょう。
いずれしても、一次二次トータルで相続税負担を考え、そこから一次相続における遺産分割を考えることが必要です。
二次相続は子供の間の争いになりがち
二次相続をあらかじめよく考えておくべきであるのは、相続税額のことだけではありません。
一次相続では通常は遺産の半分を妻が相続します。また、妻には「配偶者の税額軽減」があるので、ほとんどの場合相続税の支払いの必要がなく、居住している土地や建物の名義が、夫単独であったものから妻に子供を加えた共有名義に変わるだけ、というケースが少なくありません。
しかし、妻(母親)の死亡による二次相続では、当然ながら「配偶者の税額軽減」は使えず、また、法定相続人数も一人減ることになることから、基礎控除額も減り、相続税の負担が大きくなる可能性があると同時に、共有名義にしていた土地や建物を兄弟間でどう分けるかという問題が出てきます。
生前の両親との関係や介護の程度などによって、きょうだい間に「等分では不公平」といった不満が出てくることも少なくないからです。
相続は単に相続税対策として考えるのではなく、きょうだい間の「財産分割」をどう進めるかという観点からも、早めに取り組むことが必要でしょう。