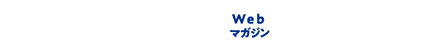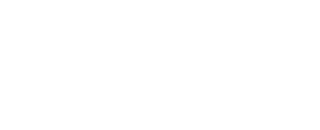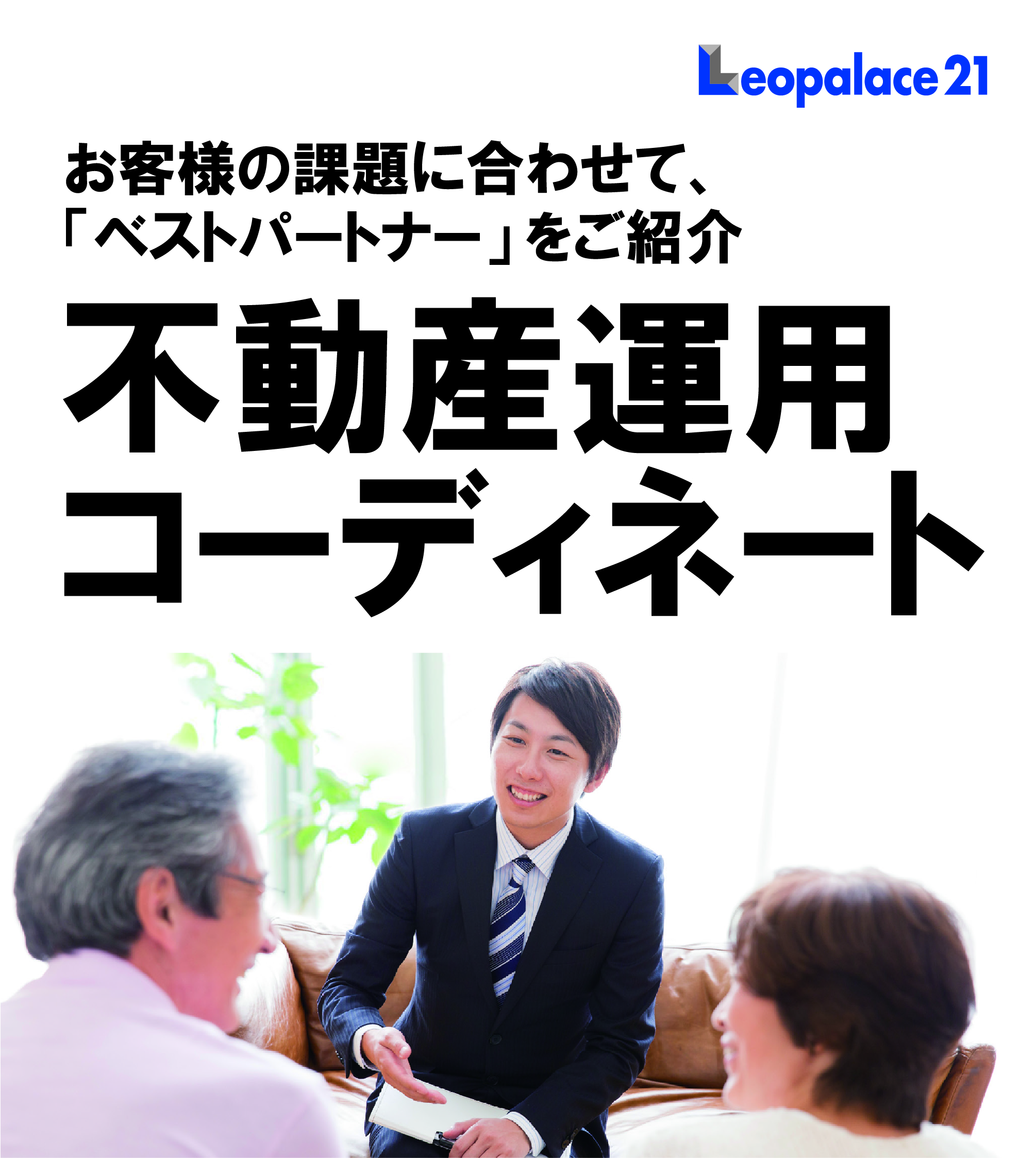実家は財産どころか「負債」になる?!
「遠方で一人暮らしをしていた親を呼んで一緒に住むことにした」「親が介護施設に入った」「両親とも亡くなった」――さまざまな理由で、実家の住み手がいなくなり、空き家を所有する人が増えています。
「空家対策特別措置法」も2015年5月に施行となりました。管理の行き届かない空き家が「特定空き家」に認定されると、固定資産税の大幅なアップや解体の勧告を受けることがあり、市町村長の命令に違反した場合は五十万円以下の過料が科される場合があります。
解体をするにも100万円を越える費用が掛かり(鉄筋コンクリート造の場合はさらに大幅に費用がアップ)、廃材・家具・ゴミの処分費も解体費用と同じくらい掛かってしまいます。
親の家(実家)を相続することは、資産が増えるどころか、対策に悩まされ、解体費・処分費の負担が発生する可能性もあり、むしろ「負債」を抱えることになりかねません。
昨今「空き家となった実家をどうするか」は、次の世代にとって切実かつ重大な問題となっています。
「空き家」対策の選択肢はいろいろあります
では、空き家をどうするか?対策は下記の表のようにいろいろあります。
| 対策 | メリット | デメリット |
| 住まいとして使う | ||
| 賃貸して収入を得る | ||
| 売却する | ||
| 解体して更地(借地)にする | ||
| 解体撤去後、事業用地として活用(商業施設等への建替)する | ||
| ひとまず現状を維持する | ||
| 寄贈する |
しかし、実際には大きな決断となり、また、きょうだいがいる場合は相続などの調整も発生します。
どの対策がベストな選択なのか、決めることは容易ではありません。
高齢化やライフスタイルの多様化が進んだことから、実家が空く頃には次の世代も年齢を重ねており、住み慣れた自宅を所有しているケースがほとんどです。また、多くの場合、実家は立地が悪く、建物も老朽化しています。
人に貸す場合も、貸す以上は相当な費用を掛けてリフォームしなければなりませんし、管理・運用という手間と費用が発生します。そもそも、旧い家に魅力を感じて積極的に借りたいと考えるファミリー層はほとんどありません。

解体して更地にするのも、解体費・家財の処分費、整地費がかかり、しかも更地のまま所有すれば、固定資産税は、家が建っていたときの3倍から最大6倍にも跳ね上がります。
特に空家対策特別措置法の施行以後は、社会的な注目が集まり、地域にとっては防災や治安、景観などの面から不安材料と見られてしまいます。早めの対策が必要になっています。
ひとまず管理を依頼し、時間をかけてしっかりと対策を練ることも
現在は空家の管理サービスを行ってくれる管理会社や不動産会社も多く、毎月、換気や通水、水漏れの確認、郵便受けの確認と報告をしてくれます。さらに、除草や簡易清掃、災害臨時対応なども頼むことができます。
これによって空家対策特別措置法の問題はおおむね解決できるのではないでしょうか。
容易に結論が出ない場合は、こうした管理サービスを利用して空き家を健全な形で維持し、つつ、結論を急がずにしっかりとした対応策を練られることもお勧めします。