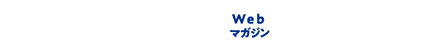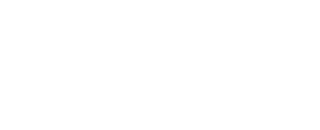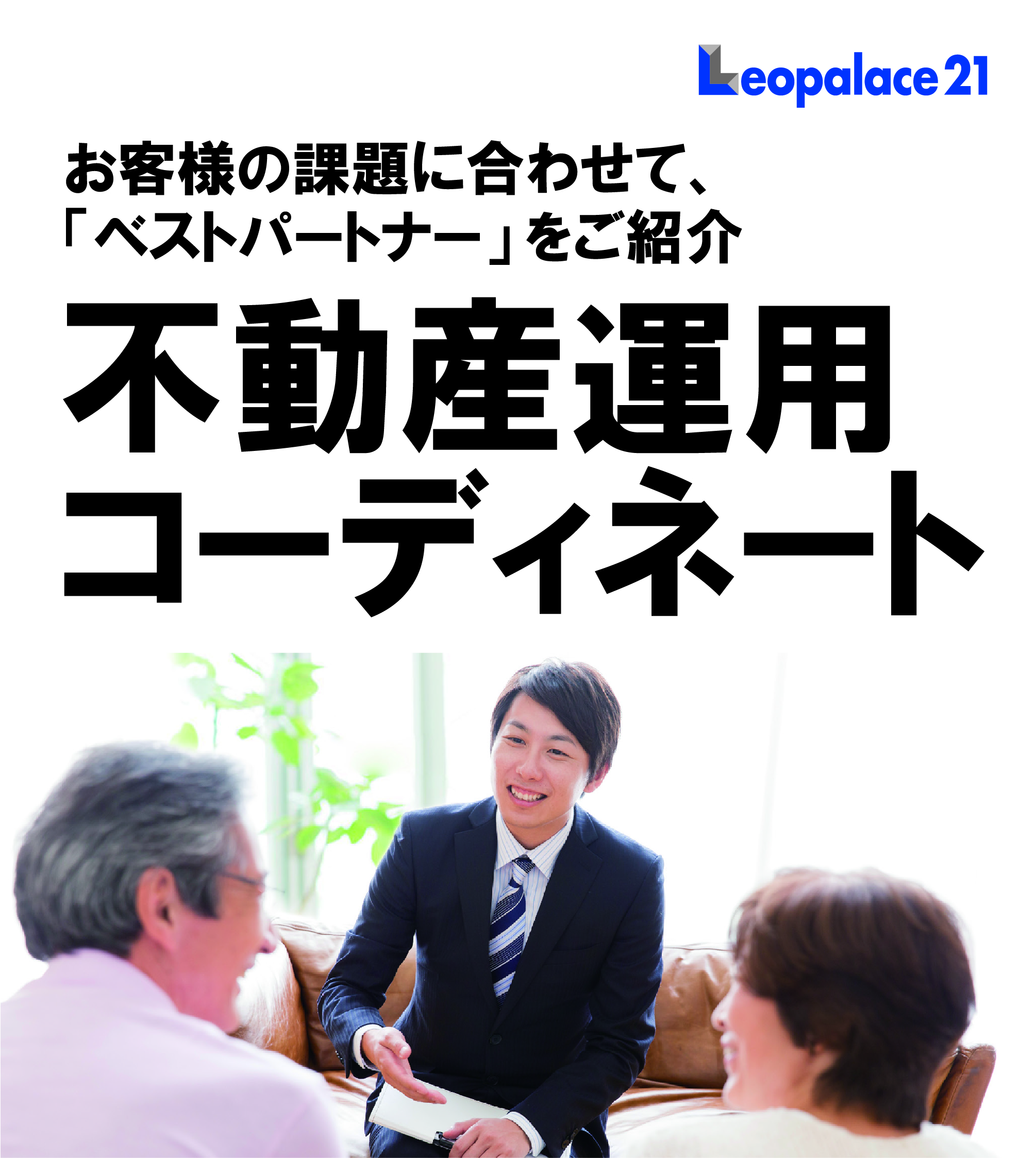空家対策特別措置法とは
現在全国に空き家は約820万戸で、住宅総数6,062.9万戸に占める割合は13.5%に達しています(2013年、総務省調査)。
適切な管理が行われていない空き家が、防犯・防災、衛生、景観などの面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていると見た政府は、2014年に「空家対策特別措置法」を制定、翌2015年5月から施行しました。
この法律に基づき、次のようなことが実施されています。
空家対策特別措置法が行うこと
- 空き家の実態調査
- 空き家の所有者へ適切な管理の指導
- 空き家の跡地についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定し、助言・指導・勧告・命令、さらに罰金や行政代執行を行う
[空家]の定義
まず法律では「空き家」を「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)」と定義。
具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て判断されることになっています。
従来は、たとえ空き家であっても、所有者の許可なしに敷地内に立ち入ることはできませんでした。
しかしこの法律では、自治体による敷地内への立ち入り調査や所有者の確認をするために住民票や戸籍、固定資産税台帳(税金の支払い義務者の名簿)の個人情報の利用、水道や電気の使用状況に関する情報を請求できるとされ、それらを通じて「空き家」が特定されることになっています。
[特定空き家]の定義
空き家の中でも「特定空き家」と認定された場合は、行政から指導や勧告、命令などを受けることになります。この「特定空き家」は、次の①から④のいずれかに該当するものです。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるもの
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態にあるもの
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態にあるもの
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあるもの
なお、特定空き家の認定は非常に重要な判断になることから、上記の空き家の状態に加え「周辺への影響の程度」も含め判断すべきものとされています。
さらに、市町村長、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者などで構成される「協議会」の意見などを聞いて総合的に判断することが求められています。
「特定空き家」に指定されると固定資産税が6倍になる可能性
特定空家に指定された場合、その所有者は自治体からさまざまな指導、勧告、命令を受けることになります。
[助言]
「庭の草木が伸びているので除草作業を行ってください」といったことが行政から伝えられる。法的な効力が無いため、対応するかどうかは所有者の判断に委ねられる。
[指導]
所有者が助言に従わない場合や、直ちに改善が必要な場合、市町村から所有者に対して指導が行われる。指導は助言よりも重く、所有者に対して適正管理を強く促すもの。
[勧告]
指導によっても状況が改善されない場合、市町村は所有者に対して状況改善の勧告を行う。勧告を受けると、その状況が改善されるまで固定資産税の優遇措置(住宅付きの土地の固定資産税は、最大で更地の6分の1)が適用されず、従来の土地の税金となる最大6倍を支払うことが必要となる。
[命令]
勧告されても所有者が対処しない場合、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令を行う。命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分といわれるもので、最も厳しい通告。命令に背くと50万円以下の罰金が科される。また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性もある。
すでに「特定空き家」の指定や勧告が行われている
国土交通省が2015年10月に行った47都道府県1,741市町に対するアンケート調査「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況調査概要」によると、すでに30の市区町村で協議会が設置済みとなっており、指導・助言が173市区町村2,448件に対して行われ、勧告も4市区町村13件、さらに略式代施行が1件実施されています。
もし空き家の状態にあるものを所有している場合、今後は厳しい指導を受けることが考えられ、また、今まで以上に近隣住民からのクレームを受けることになるでしょう。
空き家の積極的な利活用により地域のコミュニティを再生しようという動きもあります。街の資産として生かすことも考えたいものです。