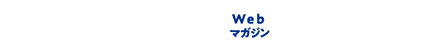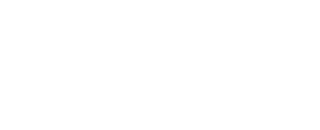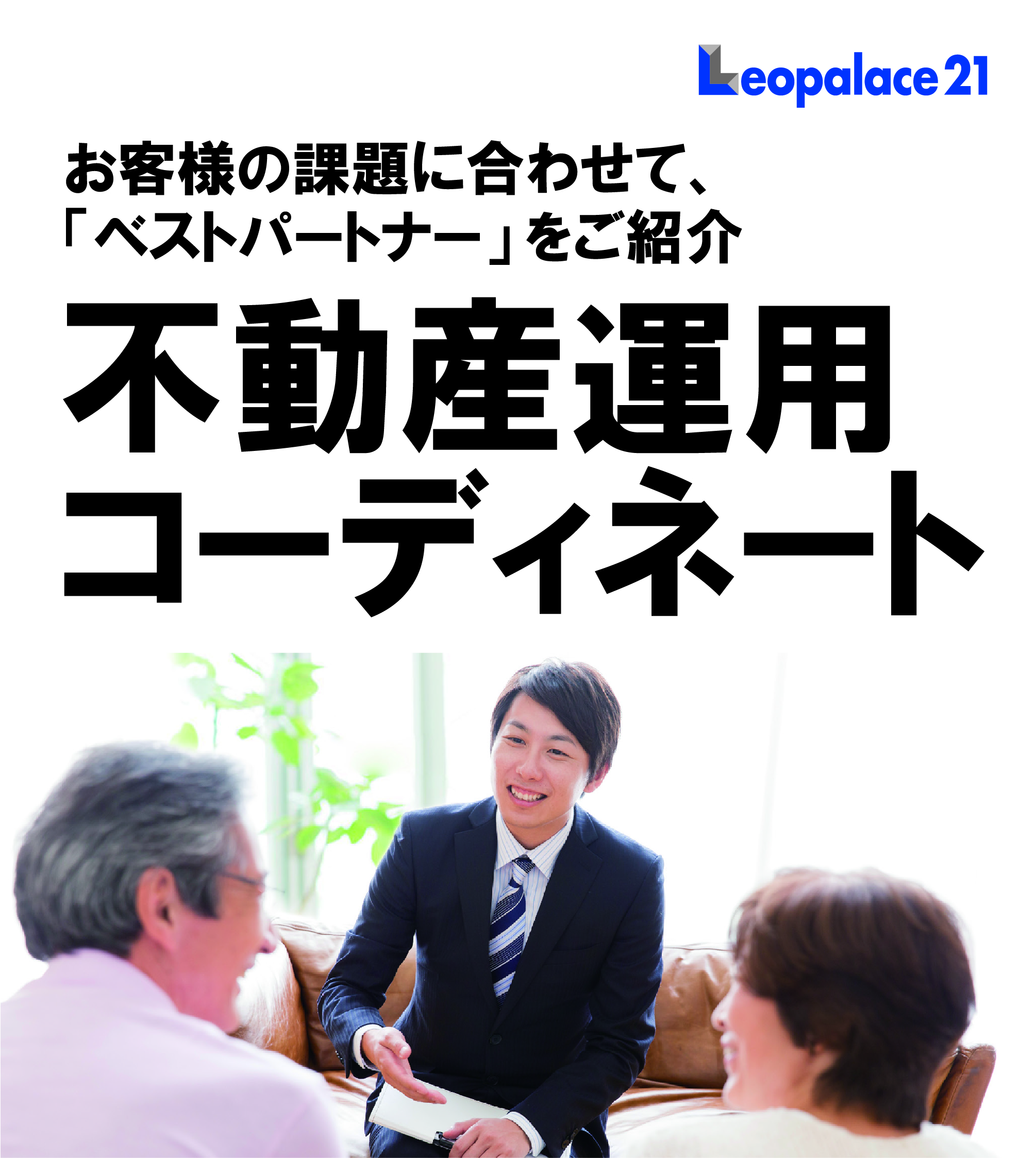都市部には「生産緑地」として指定されている農地があります。生産緑地は現在、農地以外の用途で利用することは認められていません。
しかし2022年には、自治体への買取りや、転用・売却ができるようになり、宅地が市場に溢れることが予想されています。
Leo-PRESSでは生産緑地の2022年問題について全4回で取り挙げていきます。第1回目の今回は、生産緑地とはどのようなものかを具体的に説明します。
そもそも生産緑地とはどんなもの?
生産緑地とは、「生産緑地法」によって指定を受けている、市街化区域内の農地のことです。
市街化区域にある農地が宅地化しすぎてしまうと、環境が悪化し、農業の衰退にもつながります。この対策として1991年に、都市部の一定の農地を「生産緑地」に指定して、転用に制限を設ける「生産緑地法」が制定されました。
生産緑地とされている農地の条件
- 良好な生活環境の確保に役立ち、公共施設等の敷地の用地に適している
- 面積は500㎡以上
- 農林業の継続が可能
生産緑地に指定されると、転用は認められず、農地として管理しなければなりません。また、下記のいずれかに該当しない限り、指定解除の手続きができません。自治体に報告を求められたり、立入検査等をされる可能性もあります。
指定解除の手続きが可能な条件
- 主たる農業従事者が死亡した場合
- 生産緑地として指定された後30年が経過した場合
生産緑地のメリット
固定資産税の優遇措置
農地の固定資産税は、市街化区域の区域外か区域内かによって、評価方法も課税方法も異なります。
| 評価方法 | 課税方法 | ||
| 一般農地 | 農地評価 | 農地課税 | |
| 市街化区域農地 | 生産緑地 | ||
| 一般市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 農地に準じた課税 | |
| 特定市街化区域農地 | 宅地並み課税 | ||
※市街化区域:既に市街化されているか、概ね10年以内に市街化が図られる地域。
※特定市街化区域:市街化区域の中でも、東京都・愛知県・大阪府ならびにその近郊府県にあたる区域。
生産緑地は、固定資産税の優遇措置が講じられており、一般の市街化区域の農地と比べて低い金額となります。
一般市街化区域の農地には、農地とは言っても「宅地並みの課税標準」が適用されるので、非常に高い課税が行われています。これに対し、生産緑地の場合には、「一般農地並み」の課税標準が適用されます。課税評価額の平均と10a(約1反・300坪)の固定資産税額を比較すると、生産緑地が低いことがわかります。
| 1㎡あたりの課税標準額(全国平均) | 10aの固定資産税額 | |
| 一般農地 | 67.91円 | 1,000円未満 |
| 一般市街化区域農地 | 4,214円 | 58,996円 |
| 特定市街化区域農地 | 13,086円 | 183,204円 |
※平成28年度時点での参考値
相続税の納税猶予措置
相続税の納税猶予措置が適用でき、相続人も農業を終身継続するのであれば、一定金額の相続税の納税が猶予されます。
たとえば、本来の相続税評価額が5億円だとします。納税猶予を選択した場合、相続税評価は相続税路線価ではなく「農業投資価格」にて評価されるため、本来よりも低い評価額になります。これを仮に100万円とします。
この場合の納税猶予の対象金額は「5億円 - 100万円 = 4億9,900万円」となり、評価額のほとんどが猶予対象となります。
注意点として、これは「猶予」であり、相続人が農業を途中でやめると、猶予されていた相続税とそれまでに発生した利子税を納付しなければならなくなります。終身農業を続けた場合に免除となります。